| 1. |
債務者概要 |
| 会社名 |
株式会社ハヤシマリンカンパニー |
永雄商事有限会社 |
| 代表者 |
林 永治 |
林 永治 |
| 所在地 |
長崎市波の平町4番18号 |
長崎市波の平町4番18号 |
| 設立 |
昭和47年2月 |
昭和47年2月 |
| 資本金 |
40百万円 |
30百万円 |
| 事業内容 |
中古船売買・傭船業 |
中古船売買・傭船業 |
| ホテル業・ゴルフ場 |
ホテル業 |
| 負債総額 |
約608億円 |
約128億円 |
|
|
債務者グループは、昭和47年設立。中古船売買、傭船を主業として業容を拡大し、コア事業である船舶事業(マリン事業)のほかに長崎を中心にホテル6施設、スポーツセンター2施設、ゴルフ場等を展開する地元有力企業である。
マリン事業の収益は順調に推移してきたが、バブル期の多角化、不動産投資が裏目に出て、業況が悪化。金融機関の返済はもとより一般債務の支払も滞るなど極めて厳しい状況に陥った。
|
| 2. |
これまでの経過 |
メイン行である親和銀行から企業再生協力の要請を受けたRCCは、53条買取による金融債権の集中化を進め、平成14年9月期にはメイン行との合算債権シェア65%を確保するに至り、本格的に再生検討に着手。
本件を担当したRCC再生チームは4名(公認会計士1名含む)。同チームは数次にわたり現地に赴き、現場に張り付いて、メイン行と協調しながら財務内容の精査・事業計画の策定等を実施。当初、収益力のあるマリン事業を受皿会社に営業譲渡し、メイン行の人材派遣、ニューマネー支援を受けるスキームで私的整理による再生を目指した。
しかし、多額の役員仮払金については十分な説明がなされないなど、現経営陣を維持したままでの再生は困難と判断。RCC役員が数度にわたり、事業再生と従業員雇用のため経営陣の辞任を求めるギリギリの説得にあたったが受け入れられず、平成15年7月17日、(株)ハヤシマリンカンパニーに対しては会社更生手続き、永雄商事(有)に対しては民事再生手続き開始の申立を行った。
尚、保全管理業務については現場の混乱、トラブルを回避するためRCC弁護士10名、職員17名が保全管理人補助者として協力し、通常営業の維持に努めた。
本事例は私的再生から法的再生に移行したものの、RCCとしては私的整理の中で進めていた再生スキームを、法的整理の中でもそのまま活かすことが事業価値毀損の極小化、債務者グループの迅速な再生につながるものと判断し、親和銀行の理解も得て、裁判所、管財人とも協議乃至は助言を受けながら、再建計画をまとめたものである。
当初の債権者数はホテル等の納入業者を中心に約700先に及んだが、管財人、裁判所にも申し入れを行い、小額弁済を3百万円としたことにより債権者数を大幅に減らすことができた。
東京、長崎で債権者説明会を主催したほか、メイン行と連れ立って個別債権者を複数回にわたって訪問し、再生の必要性と計画の詳細を説明。一般債権者も含めた全債権者の同意を取得し、10月20日東京地裁より改正会社更生法に基づく計画外での営業譲渡許可を得た1号案件となった。
本件は主要債権者であるRCCと親和銀行が、営業譲渡による再生計画を立案し、その他債権者の同意取付を実行した債権者主導による会社更生手続きとなった点で意義深い案件である。
営業譲渡期日は12月末日の予定であるが、メイン行である親和銀行と連携し、RCCの中立性を背景に調整能力を発揮した結果、事業価値を毀損することなく営業譲渡を実現し、親和銀行の支援のもと事業再生が始動することになる。
|
| 3. |
再生スキームの概要 |
| 金融債権をRCCに集中化し、メイン行と協調しながら、コア事業の再生を推進する。 |
|
| (1) |
収益力のあるマリン事業を受皿会社に営業譲渡( 対価は債務引受 )し、キャッシュフローから最大限の弁済を受ける。 |
| (2) |
残存会社は、ノンマリン資産処分後に清算する。 |
|
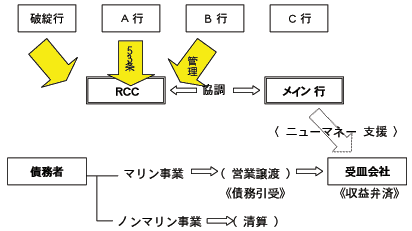 |
| 〜 RCCの役割 〜 |
|
(1) |
債権の集中(53条買取 3行・管理信託受託 1行)⇒ メイン行との合算シェア 65% |
| (2) |
コンサルタント会社も活用した財務内容の精査、再生計画の策定。メイン行との調整、債務者説得 |
| (3) |
保全管理人、管財人支援。裁判所との密接な協議 |
| (4) |
一般債権者を含めた全債権者への働きかけ及び同意取得 ( 小額債権を含む当初債権者約700先を整理し、金融債権者 14先、一般債権者 7先から債権計画 の同意を取得) |
| 〜 メイン行の役割 〜 |
|
(1) |
RCCへの債権集中化の働きかけ |
| (2) |
債権者の同意取得協力 |
| (3) |
受皿会社への人材派遣、ニューマネー支援 |
|